魚を調理する際の工程として、よく目にする霜降り(湯引き)のやり方をまとめます。
知っておくことで、魚をよりおいしく、簡単に調理できるようになります。
霜降りと湯引きの違いと目的
霜降りと湯引きは、どちらも熱湯で食材の下処理をする工程を指すものですが、目的と仕上がりに違いがあります。
霜降りは、食材の臭みや余分な脂・ぬめりを取り除き、身を引き締める目的で行われます。霜降りを行うと、食材の表面が白くなるため「霜降り」と呼ばれています。
一方、湯引きは、食材の表面に熱を通すことで、食材を柔らかくしつつ風味を引き出す目的で行われます。食材の表面のみを熱するため、熱湯にくぐらせたら冷水で身を引き締めます。そのため、食材の内側は生のままとなります。
霜降りと湯引きは厳密には異なる目的のために行われますが、作業工程はほぼ同じです。
食材による目的に違いが、言葉の表現の違いにつながっています。
霜降り(湯引き)の方法・手順
霜降り(湯引き)のやり方は以下の通りです。
①魚の切れ身を霜降りする場合、切れ身の両面全体に塩2つまみふります。
魚の切れ身を冷蔵庫で10分寝かせて、塩をなじませます。
②鍋にたっぷりの水を入れて加熱し、沸騰させます。
③お湯が沸いたら火を止め、3分ほどお湯を冷まします。
④魚の切れ身を霜降りする場合は、お湯に魚の切れ身を入れます。
魚一匹を丸ごとなど、多量の魚を霜降りする場合は、ボウルやトレイに魚を入れて、お湯を回し掛けします。
⑤表面が白くなったら氷水に魚を入れます。
冷やしながら魚の表面についた汚れ、血合い、鱗を指でこすって洗い落とします。
魚一匹丸ごと霜降りする場合は、おなかの中も洗うようにしましょう。
⑥表面の汚れを落とせたら、キッチンペーパーで水気をふき取りましょう。
霜降り(湯引き)を活用するおすすめ料理
霜降り(湯引き)は、特に煮魚を作るときに行います。
焼き魚や揚げ物は、加熱時の温度が高く、臭みの元になる脂や血合いが調理工程で落ちるため、魚特有の臭みを感じにくくなります。
一方煮魚は、素材そのものを水やだしの中で火を入れるため、加熱温度が低く、臭みや風味がそのまま煮汁などに移りやすくなります。そのため、霜降り(湯引き)をすることで臭みを取りのぞく工程が大切になります。また、煮魚は煮崩れしやすい調理方法のため、あらかじめ湯引きで身を引き締めることで、煮崩れを防ぐ効果もあります。


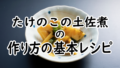

コメント